真夜中の金魚~中畑姉弟の夏~ |
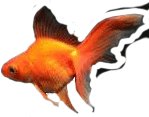 |
#2. |
|---|
その、真夜中。
直己は唐突に目を覚ました。
布団に転がったままの格好で、んー?と考える。
(まだ真っ暗やん。なんで、目ぇ覚めたんや?)
―― 昼間の話が気になった訳でもないだろうが。
何故か、その後妙に寝付けない。
何度かモゾモゾ身じろぎしたり、ころん、ぱたんと寝返りを打って、とりあえずトイレに行く事にした。
二階の子供部屋から階段を下り、用を足して戻ろうとしたが、ちょっと喉も渇いていたので台所に寄って麦茶を飲んだ。
そして部屋に戻るべく足を向けた、その時。直己は鈴の音を聞いたような気がした。
つい、びくりと身を強張らせて耳を澄ます――
何も、聴こえなかった。
(なんや、気のせいか)
気になどしていないつもりだったが、実は怖かったのだろうか? 自分は。
もう、大きいのに。他人に知られたら、ちょっと恥ずかしいかもしれない。
(特に、お姉ちゃんには知られたぁないな。何言われるか、わからへん)
そんな事を考えながら、廊下を歩き始めた直己の耳に、今度ははっきりと、鈴の音が届いた。
思わず足が止まる。
鈴の音は、まだ続いている。金属質で澄んだ、重い音。
それは鈴というより、むしろ風鈴のようだ。
余韻と反響を持って、重なる風鈴の音。音だけ聴けば、涼やかで美しいのだけれど。
風鈴?
(なんや、そうか。そうやんな)
風鈴なら、今の窓辺に在る。
金魚を掬った同じ日、美鶴が買ったやつが。
南部鉄、というらしいその風鈴は、重くて釣鐘型をしていた。お金を払った父が、「えらい渋いのん、買うたなあ」と笑っていたっけ。
納得して、今度こそ寝る構えをとる。安心したら、怖がりかけた自分が可笑しかった。
(―― 本当にもう、我ながら)
通りすがりに居間をひょいと覗き込むと、澄んだ余韻を一音残して、風鈴の音はそれきり途絶えてしまった。
直己は、ぱちぱちと目を瞬いた。
いきなりしん、と静まり返った室内は、妙に居心地が悪い。おまけに、今夜、現在に限って、通りを通る車の音や、人の声すら聞こえない。
居間には、金魚鉢。
その鉢が、載せられているリビングボードは窓の際。
そしてその窓の外には、風鈴が吊るされているはずだった。
―― 人間が居る間は金魚は鳴かない、と小母さんは言った。
でも、それを言うなら金魚は最初から鳴かない。
鳴かないものなのだ、絶対。
(常識やん)
それなのに。
じわり、じわりと―― 何かが自分の身体に入り込んで来ているような、気がする。
それは、恐怖という感情だ。
あれは迷信というヤツで―― いや、そうじゃなくて。あれは嘘、デタラメだと解っているのに。
なんで、怖いんだろう?
(―― 小母ちゃんは、フザけただけや。聴こえてたのは、風鈴の音)
それなのに。
(ボクが入った途端に止んだのは、偶然)
それなのにどうして、金魚が鳴いていたのかもしれない、と思うのだろう?
―― 風鈴が――
もう一度、鳴ればいいのに。そうすれば、やっぱり笑い話で澄むから。
情けないかもしれないが、直己は本当に怖くなってしまったのだ。
あの時、やはり喉の渇いた美鶴が麦茶を飲みに来なかったら、直己はそのまま朝まで立ち尽くしていたかもしれない。
「―― 何。そやったん?! やっぱ、アホやわ、アンタ」
ハーゲンダッツのキャラメル味アイスクリームを掻き取りながら、情け容赦なく、美鶴。
「―― て、言うか、臆病者なんやから。しゃあないな、ホンマ。いーや、ヘタレ。ヘタレのタレちゃんや!」
「―― 昔の話や」
いつまでも続きそうな罵倒に、苦々しく困りきって、直己が遮る。
南部鉄の風鈴が、ちりーん、と鳴った。
それは先日、祇園際に行って来た、やはり美鶴が買ってきたものだ。
京都に行ってまで南部鉄にこだわらなくてもよさそうなものだが、昔窓辺に吊るされていた物と、それはよく似ていた。美鶴なりに、気に入っていたのかもしれない。
同じように居間の縁側に吊るされたのを見て、たまたま思い出した直己が話題を向けたら、真実を知った姉に、思い切りバカにされてしまったワケだ。
(アイスくらい、黙って食えや、まったく)
いまや自分は中学生で、美鶴は高校生になっているというのに、相変わらず姉に頭が上がらない。
流石に最近は昔ほどムキにはならず、あまり派手な喧嘩はしなくなったが。
「せやけどなあ、あん時はホンマに怖かってんで」
ぶーたれて尖らせた口で、コーラのペットボトルを迎えに行く。
「せやから、臆病者。『幽霊の正体見たり、枯れ尾花』て、知ってるか?」
「はいはい、風鈴やろ、ホンマは。解っとるがな」
「違う。しょーもない事、びくびく怖がってるから、幻聴なんて聴くんや」
「幻聴?」
心外な、と直己は片眉を吊り上げる。
「せや。そんな音、聴こえるハズあらへん。あの風鈴、そん時、鳴るはずなかったんやから」
「はあ?!」
「だって、あれな。買うた次の日に短冊、千切り取られてしもうたんやで」
「誰に!?」
意外な告白に、思わず声が大きくなる。
「セイちゃんちの猫(ミー)。パトロール中のあのコがみつけて、喜んでじゃれよってん。ほんで」
「……」
そこまで喋って、美鶴は溶けかけたアイスクリームを慌てて食べ始める。
直己は、といえばコーラを持ったまま、しばし固まっていた。
―― 翌日には鳴らなくなっていた?
件の夜は、三日目。美鶴の言う事が本当なら、確かに風鈴は鳴るはずがない。
金魚が鳴かないのと同じくらい、確かに。
(―― そんなら。オレが聴いた鈴の音は、何処から聞こえてきたんやろう?)
美鶴の言うように、幻聴。というか、気のせい。
もしくは、たまたま近所の風鈴が鳴っていた。
それとも。本当に金魚が鳴いていたのだろうか?
それらを明らかにする術は、もう無いのだけれど――
「コーラ、温(ぬる)なるで」
美鶴の声で、現実に引き戻される。
この姉の、こんなところも、ちょっとは有難いかもしれない。本人には言えないが ―― いや、言ってなどやらないが。
頭をぶんぶん振ると、直己は残っていたコーラを一気に呷(あお)り―― 咽(むせ)た。当然といえば当然だが。
炭酸の抜けたコーラは、その分激烈に甘かった……
美鶴がそんな弟に冷たい眼差しを送りつけていると玄関の戸が、からからと開いた。母が買い物から帰ったらしい。
「ただいまー。見て、見てー」
母は語尾にハートマークが付きそうな程、ご機嫌で入ってくる。
「何ー?」
アイスクリームを食べ終わった美鶴が空き容器を出すついでに覗きに言って、あ、と声を上げた。
「可愛いやろ? スーパーの前に、売りに来とったんよ」
母は居間の直己にも、ほらほら、とぶら下げた手荷物を示して見せた。その小さなビニール袋の中には、
紅い着物(おべべ)の、可愛い金魚。